日本の城跡
首里城(別称:中山城)
略史 13世紀末から14世紀のグスク造営期に造られ、14から15世紀初頭の三山時代には中山の城であった。尚巴志が三山を統一し琉球王朝を立てると、首里城を王家の居城とした。そして首里は首府として栄え、第二尚氏においても変わらず、王国の政治・文化・外交の中心的役割を果たした。首里城は王位争いなどで数度にわたり焼失しており、財政逼迫から薩摩藩から原木等の提供を受けている。現在見る首里城は三度目の火災から再建された1715年から戦前までの姿の基にしている。明治時代の沖縄県設置により、首里城は政府の所在地としての役割を失い、日本陸軍の第六師団(熊本)の軍営となった。その後首里区に払下げられ学校などに利用された。王宮でなくなった首里城は急速に荒廃、老朽化が進んだため昭和初期の保存運動により正殿の改修工事され国宝に指定された。しかし太平洋戦争中の沖縄戦において日本軍が首里城の下に地下壕を掘り陸軍32軍の総司令部を置いたこともあり、連合国軍の激しい艦砲射撃、その後の激しい戦闘で首里城や城下町・宝物・文書が破壊・焼失した。戦後、守礼門が再建され、日本復帰後に歓会門と周囲の城郭が再建、更に琉球大学の移転により本格的再建計画がスタートした。そして2000年には首里城として他のグスクとともに”琉球王国のグスク及び関連遺産群”の名称で世界遺産に登録されている。 |
| 沖縄の城(100以上あるといわれるグスク)の特色(大陸起源である。) ・石垣が複雑な曲線を描いて続き、勾配も垂直に近い急なもので、反りがない。 ・城門は石造アーチ式の門を用いる。 ・城門には木造の楼閣を上げるが、隅櫓のような建物がない。 ・水堀がない。 ・首里城の正殿などに見られるように、日本の書院造の御殿とは異なり、中国や韓国の宮 殿建築に類似する。 |
 |
 那覇空港 |
 同内部より |
 左に園比屋武御嶽石門と歓会門方面 |
|
 龍潭池方面 |
 歓会門・石垣 |
 同 |
 同石垣 |
 同のシーサー |
 同 |
 瑞泉門へ |
 同 |
 龍樋 |
 瑞泉門 |
 途中の冊封七碑 |
 瑞泉門内部 |
 同の曲線の石垣 |
 久慶門 |
 同・石垣 |
 漏刻門 |
 同内部 |
 同石垣と久慶門 |
 同から円覚寺方面 |
 万国津梁の鐘 |
 同から正殿方向 |
 広福門と漏刻門 |
 広福門内部 |
 首里森御嶽 |
 用物座 |
 左が京の内 |
 琉球の踊り |
 泰神門 |
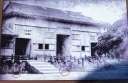 |
 北殿 |
 南殿・番所 |
 正殿 |
 正殿前の大龍柱 |
 京の内の石垣 |
 奥書院 |
 鎖之間庭園 |
 御殿 |
 継世門方向 |
 王座 |
 玉座 |
 王冠 |
 国王印 |
 内部 |
 右掖門 |
 真玉森御嶽 |
 同 |
 同 |
 西のアザナから |
 同 |
 同 |
 西のアザナ方面石垣 |
 木曳門 |
 同 |
 西のアザナ方面石垣 |
 同 |
 琉球大学跡記念碑 |
 首里城碑 |
 木曳門前広場より首里城方面 |
 龍潭池からの首里城 |
 石畳坂 |
 同 |
 祈り大木 |
 同 |
 金城大樋川と村屋 |
 金城大樋川 |
 沖縄の花 |
 同 |
 同 |
 同 |
 同 |
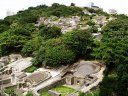 沖縄の墓地 |
 同 |
|||
 |
||||